
温暖化ショックとオイルショックと
01/16/2011
目次
1973年、いわゆるオイルショックがおきた。1973年10月に第四次中東戦争が勃発し、OPECに加盟のペルシア湾岸の産油6ヶ国が、原油公示価格を1バレル3.01ドルから5.12ドルへ引き上げると発表した。さらに12月には、1974年1月より原油価格を5.12ドルから11.65ドルへ引き上げた。要するにある日突然原油価格が4倍に上がった。
その結果、トイレットペーパーや洗剤などの買占め騒動やデパートのエスカレータの運転中止、テレビの深夜放送の休止、ネオンサインの早期消灯、ガソリンスタンドの日曜休業、プロ野球のナイター時間の繰り上げなどの省エネルギーが実施された。また代替エネルギーの開発が叫ばれるようになった。
省エネルギーと代替エネルギーへの関心は、20世紀後半から今世紀へかけて起きている「温暖化ショック」と良く似た現象である。「温暖化ショック」と言っても、買占めのような個人の生活を脅かす騒動が起きていないから、大半の人々はまだ冷静である。
オイルショックは資源枯渇という本質的な問題があるのだが、政治的要因の大きなできごとだった。温暖化ショックはエネルギー問題を背景にした科学的解釈がからんでいる。70年代以降叫ばれるようになった「地球にやさしい」生活様式というスローガンのもと、多くの一般市民の掛け声が多く聞かれるのはオイルショックとは違っている。ただ、一時的ブームのもと冷静な科学データの解釈がないのは残念である。
温暖化ショックの問題は外交問題ともなっている。従って、裏の要因も解析しながらの外国との対応がある。政府および研究所を含む国立の機関は、温暖化の原因が必ずしもCO2ではないことを掴んでいるはずだが、そうした裏の考え方は今のところ出てこない。科学の問題が政治問題にすりかえられているのは残念である。
この歳になった多くの人々が回顧に浸るように、私も若干の回顧に浸りながら二つの問題を考えてみたいと思う。
生まれたのは、山口県岩国から一時間半程度バスで入った山の中だった。岩国、広島へ出るバスは一日数本だったから子供心で感じる都会は遠かった。親爺が勤めていた日本鉱業、河山鉱山から大分県の佐賀関の精錬所へ粉砕した鉱石は、ダンプカーで岩国まで搬出されていた。ダンプカーの運転手の何人かが、娯楽のない当時、麻雀をするため私の家へ出入りしていた。バスの便がない時はその顔見知りの人達に頼んでおふくろは同乗させてもらっていた。指を詰めた人もいた。親爺の言ったところによると、その人の前で、よく指を縮めて牌を混ぜるまねをしたらしい。私はまだ、小学校へ入る前の幼児だった。

小学校へ入る前で記憶の鮮明さから思うと 6 歳の時だろう。岩国の錦帯橋のそばでくじらの博覧会があった。博覧会が催されるほどくじらは良く食卓のぼった。ライスカレーでは牛肉など使わず必ず鯨肉、酢味噌で食べる白いベーコン、そして刺身も良く食べた。博覧会の時の、赤いニッケの入った飲み物の小瓶を顔に寄せた錦帯橋のそばの写真が残っている。錦帯橋は河山から岩国へ入るところにある。恐らく今日も昔の工法が現存していると思う。釘は一本も使われていない。こうして年をとり実際に見た多くの建造物と比較しても、その橋はなかなか優美であった。錦川を錦帯橋で渡った小山の上に城跡があった。橋の手前が城下町となっていた。
ある午後も遅くなったころ、数人が橋の上から下を見ていた。当時は少なからず乞食がいた。経済成長とともに乞食を見ることもなくなったのだが、いつの頃かホームレスという形で現れた。その乞食は親子三人だった。橋の下で雨露をしのいていたらしい。見物人は家族の会話を上から聞いていたのだろう。どうやら父親は眼が見えないようだった。それ以外は何もこれといった記憶はないのだが、なぜかその光景が 55 年経った今、強く印象に残っている。私にとり城下町と言えば、錦帯橋の上から見た乞食家族の情景と、眼の赤い美しい天然記念物の白蛇である。
1950年代半ば、岩国港から大竹の海岸地区に工場建設が始まった。その一部の、山口県としては東の端に、日本鉱業は河山からの鉱石の一部を精錬するために新しい工場を作りつつあった。その要員として親爺は 1957 年(昭和 32 年)に河山から岩国へ転勤した。工場の西側は興亜石油の精製所が、東の大竹地区には三井石油化学がコンビナートの建設が進行していた。1958年、その精製所が完成して、精製所の側の岩国港へ石油タンカーが入っった。4 万 7000 トンの麻里府丸という当時としては日本一のタンカーだった。そのタンカーを見学した強い印象を今でも思い出す。
他の山陽の町と同様、岩国は山と瀬戸内海に挟まれた狭いところである。山陽線と海のそばを通る国道2号線に挟まれたところに、私が通っていた装港小学校があった。小学校のそばにトンネルがあり、山陽線を走る列車はトンネルを入る前に汽笛をならした。数キロ離れた米軍基地からは頻繁に飛行機が飛び立っていた。グランドのそばの国道2号線は当時でも交通量の激しいところだった。1957年10月にネール首相が来日した折、学校の前の国道2号線を通った時総出で歓迎したのを覚えている。なぜあのようなところを通ったのかはわからない。
家から1キロのところに和木村があった。その村の海岸に三井石油化学のコンビナートができて、多額の法人税が入ることから岩国とは合併しなかった。当時でさえ、街中の道は和木村に入ると舗装されていた。現在も和木町というから合併していない。
私の家族は、社宅が出来上がるまで田んぼの中の典型的な農家の家を借りて住んでいた。五右衛門風呂、玄関、キッチンの土のたたきなどを思いだす。近くの神社で秋祭りがあった時には、歌舞伎の類なのだろうか、夜遅くまで躍っていた。歳を取るにつれて感動するものも当然少なくなるのだが、あの秋祭りほど興奮した祭は以後見れなかった。出来合いの祭という色彩が濃すぎるのかもしれない。
工場の前の田んぼを埋め立てて社宅のアパート群が一年程度でできあがり、多くの人が河山から転勤してきた。その中に同級生のU君がいた。お互い顔は知っていたようだ。社宅予定の奥のアパートは出来上がっていたので、そこに引っ越してきたのだった。彼のお父さんの顔は良く知っていた。河山の一番大きい小壁社宅地区は、川を渡ってなだらかな山の斜面に連なっていた。その川を渡った入り口の右側に守衛所があってそこに勤めていた。だから学校などの行き返りの時など、良くお会いした。
学校の授業の時間割が違って帰りの時間が異なる時は、彼の授業が終わるまで廊下で待っていて一緒に帰宅したものだ。彼の担任の「原」先生があとどれぐらいで終わるか時々教えてくれたものだ。私の家族が1959年(昭和34年)に福島県に転居するまで、殆ど一緒に遊んでいたように記憶する。ベービーブームの世代だが、本当に多くの子供が社宅のアパートにいた。私の妹とU君の弟も同じ年だった。ある午後、かきもちをさいころ状に切って、フライパンで焼いたあられを上田君のおかあさんが作ってくれた。鮮明に記憶に残っている。当時のおやつはこのようなものだった。一時間弱程度の沖合いに宮島があった。上田君の家族がさそってくれて一緒に行った。島へ渡る一部の船は、ガラス張りの海底を見ることのできる覗き窓のついた座敷になっていた。そこに靴を脱いで入ったら、私だけが靴下もはかず、はだしで何となくばつが悪かった覚えがある。
あれから半世紀、私の両親は五度、私自身も大学および就職してからも10回程度の転居をしている。大学時代の友人とは連絡がつくのだが、高校以前の幼ななじみはU君を除いて皆無である。
バルチモアにいる時にU君から、2000年の正月のたよりに、今年は訓練の一環で世界を回ってニューヨークに寄るので会えないかと言ってきた。春頃これから出航だと突然 e-mail で連絡があった。会うには日時、場所を指定しておかないといけない。アメリカは広い。彼は洋上のはずでどうやって連絡したものか思案した。試しに e-mail で同じアドレスへ返事をしたら彼の船へ届いた。どうも通信係りがいてそこを通して彼に伝わったようだ。数回ののやりとりで彼が艦長をしている船がヨーロッパを回って近づいてくるのがわかった。
後で知ったことだが、2000年7月4日、20世紀最後のアメリカ独立記念日を祝う洋上式典に参加するため、世界各国の帆船170隻、海軍の艦艇70隻がニューヨーク港に集結した。U君が乗る練習艦「鹿島」もそのうちの一つだった。7月4日の前日ではなかったのだろうか。セントラルパークのそばにあるホテルで落ち合うことができた。それから停泊中の「鹿島」へ行った。港では、NY市の警察が厳重な警備を敷いていた。私たちの乗った専用車はシェパード犬のチェックも受け、一般市民は通行禁止の区域を抜けて、停泊中の船の近くの埠頭まで運んでくれた。「鹿島」が停泊していた。
隊員の訓練を兼ねた鹿島は、時々、皇室関係者の高覧があるという。その部屋は優雅で美しく、波間に千鳥が舞う模様の絨毯が敷かれていた。続く風呂場は、総檜作りであった。個人的にはそこまでする必要があるのかと言うぐらい比較的小さな船に作られてあった。阿川弘之氏から寄贈の置物もあった。「鹿島神社」の写真もあった。私が鹿島に近い矢田部にいた時、娘の七五三で行ったことのある神社である。二時間程度過ごして食事に出た。「クイーン・エリザベスII」と軽い接触事故があって、その挨拶で訪問客があるからと10分程度待った。この接触事故のもようは、後で文藝春秋2000年11月号に掲載された阿川弘之氏の文で知った。
翌日の5日(日時のずれがあるようだ)、英国の豪華客船「クイーン・エリザベスII」が入港。しかし折悪しくも2ノット半の急流となっていたハドソン河の流れに押された巨大な客船は、係留中の「かしま」船首部分に接触した。着岸した「クイーン・エリザベスII」からすぐさま、船長のメッセージを携えた機関長と一等航海士が謝罪にやってきた。その時の「かしま」艦長、U一等海佐(海軍大佐)の答えは… 「幸い損傷も軽かったし、別段気にしておりません。それよりも女王陛下にキスされて光栄に思っております」。この発言が船乗りたちの間で評判となり、ニューヨークのみならずロンドンにも伝わって「Times」などが記事に取り上げたそうだ。今も Web で検索するとヒットする。
私が小学校3年の1958年に岩国港東側の興亜石油のフレアースタックから炎が燃え始めた。一ヶ月遅れて、瀬戸内海を越えた四国でも、石油化学がスタートした。こちらのフレアースタックの炎は、17年後に毎日見ることになる。というのは、1975 年 4 月住友化学へ入社して愛媛県の新居浜へ赴任したからである。
地方都市であるが、新婚生活、就職、初めての四国での生活と人生での大きな節目だった。当時流行っていた「瀬戸の花嫁」の歌を聞くとそうした気持ちをなつかしく思い出す。もちろん、初めての町だったのだが、何度か訪れたことのある懐かしいようなところだった。生まれたところは、鉱山業を中心に谷間にむりやり村を作ったところだった。家は小さな川沿いに点在し、斜面の上まで社宅があった。新居浜は住友銅山から発達したところで、その廃坑のあったところへ数時間かけて登ると斜面に昔の社宅のカマドの跡がまだ残っていた。その跡を見た時には幼児の時の社宅を思い出したものである。
日本鉱業の岩国の工場は、興亜石油と三井石油化学の間に位置していた。現在、三井石油化学は三井化学となり、日本鉱業のあった地区は全て三井化学になっている。当時、工場前に新設された社宅のアパート群も三井化学のものになっている。Google の航空写真でその地区を拡大して見ると、私の家族が住んでいた社宅もまだ残っている。
次第にエネルギー源は石炭から石油へと変化し、石炭需要が落ち込み始めた。三井鉱山などにみられる炭鉱の労働問題へと発展する。1960年前後には殆ど毎日のニュースで取り上げられていたのを思い出す。このエネルギー転換と化学工業の構造的変換を通ってオイルショックが来るまで、日本経済の高度成長へとつながる。
新居浜へ滞在していた1982年に、三井石油化学の大竹の工場を山から眺める機会があった。もう時効だから明かしても良いだろう。当時住友化学の工場でC4留分を酸化してアクリル酸を合成するプロセスを開発していた。三井石油化学では一足先に工業化していて、大竹にそのプラントがあった。そのプラントを小高い山の上から写真に撮るをいう出張だったのである。その出張のおり、川を越えて岩国側へ移動し23年ぶりに、昔住んでいた社宅を外から眺めることができた。
相前後して各化学メーカーでエチレンをベースにする石油化学が始まった。どういう因縁か、住友化学に入社して4年後に言わば競争相手の、三菱油化、昭和電工、出光興産、東洋曹達の人々とエチレンを作るプロジェクトで共に合いまみれることになる。それは、岩国のフレアースタックに炎が燃え始めてからちょうど20年後であった。
他の化学メーカーと共にエチレンを作るプロジェクトを始めることになったのはオイルショックが原因である。その前後のことを少し述べねばならない。
岩国、新居浜の3万2千トン/年のエチレン生産量で始まった石油化学が、安い原油の恩恵で、1958年から1974年までに約400万トンの生産量までに成長した。オイルショック前の原油はバーレル3ドルだったから、1$ = 100 円で計算すると2 円/L 弱という安さだったのである。
1973年から1974年にかけて原油価格が4倍になった。原油価格高騰は、第四次中東戦争がきっかけという極めて政治的な要因が端緒となった。しかし、当時環境問題と資源問題が徐々に関心を持たれるようになってきていて、有限の石油資源および石油の安定確保に向けて関心が持たれ始めた矢先だった。
エチレンはナフサを熱分解して作られる。ナフサというのは、原油を蒸留して得られるガソリンと同じ沸点領域の留分である。原油からは10%弱の収率である。残りの90%以上は、究極的には燃料となって燃やされる。

上記のグラフは大まかな各石油留分の収率で、原油の性質により大きく変わる。あくまで概念的なものである。原油は蒸留されて各沸点の留分で分けられる。ナフサのみが化学原料に供される。700℃以上の温度、1秒前後の短時間で水蒸気と共に熱分解される。最も需要のあるエチレン、プロピレンを含んだガスが生成する。熱分解生成物を出発点に延々と石油化学が始まる。ここまでは良く確立された化学であるが、ナフサ分解だけを取っても付帯設備を入れると非常に大きなプラントになる。装置産業と言われる所以である。プラントの設計から試運転、操業と私のような化学屋が立ち入る隙はない。
軽油留分をさらに水素化分解、精製して200℃以下のものがガソリン、200℃よりやや重いものまでがディーゼル燃料として使われる。植物由来のエタノール、植物および動物の油脂から合成したディーゼルを代替燃料として利用するために現在ホットな課題として研究されている。植物由来だからCO2は増えないということだが、原料、生産の規模を考えると全くの気休めである。
原油を蒸留すると半分以上が蒸留されずに残る。スチームエジェクターなどを蒸留塔に連結して蒸留する圧力を下げると、より重たい留分を蒸留することができる。それでも1/4 以上を蒸留できない。これらは蒸留残油である。この蒸留残油からエチレン、プロピレンの化学原料を作るプロジェクトがオイルショックを契機に始まった。「重質油分解によるオレフィンの製造技術」 である。通産省の工業技術院がスポンサーで即ち全額国民の税金を使ってのプロジェクトであった。
民間6社で、「重質油化学原料化技術研究組合」が設立された。当初の予算が120億という大きなもので、茨城県の鹿島の三菱油化の敷地内にデモンストレーションのプラントが建設された。1979年運転要員のひとりとして新居浜から鹿島へ転勤したのである。翌年にプラントが竣工した。今年その30周年記念ということで当時のメンバーが鹿島へ集まったのだが、私は遠隔地で参加することはできなかった。
鹿島は砂漠の中に作られた工業地帯である。しかも、車がなければ生活できないような田舎である。鹿島臨海工業地帯造成計画は砂漠に巨大な人工掘込港湾を建設した国家プロジェクトであった。東京オリンピックが開催された年に開発が始まった、またその年に新産業都市に指定された新居浜市も、受験科目の地理の一応頭に留めておく必要のある項目の一つであった。大学を卒業して両都市に住む偶然が巡ってきた。
これら鹿島、新居浜のアパートで物心つくまで育った娘が2006年の五月に結婚した。その娘がアイルランド出身の青年と結婚することにならなければ、北海道と同規模のこの小さな国を知る機会はなかった。ニューヨークに住んでいる二人が、結婚式をアイルランドで挙げると知らせてきた。かくして五月、妻と私は十日間のアイルランドの旅に飛び立った。三つ葉のクローバー、映画「タイタニック」の移民達、リバーダンス、Enya の Celtic 音楽、歌手ボノのアフリカ支援‥この国についての私の知識は、もちろん断片的で乏しかった。
首都ダブリンで車をレンタルし、半島や湖の周辺、古城や町を歩いた。その散策のおり、ディングルという鄙びた半島を歩いた。この突端から丘の頂上まで、羊や牛が悠々と放牧されている岬を歩いていて、「ライアンの娘」という映画の記念碑を見つけた。撮影当時の坂、石垣、草木は映画の中のものでなく今もありふれたアイルランドの風景であった。この映画は学生時代にたまたま孤独を紛らわすためであったのか、100 円の名画座で見たのであるからもう 30 年以上前のことである。ストーリーは当事良く解らぬまま、大画面に映る若い娘が村人から長いしなやかな髪を切り取られる最後の方のシーンがやけに頭に残っていた。映画の中の嵐の景色と今も耳に残る音楽に浸る時間には人生の偶然を感じざるを得なかった。

便利な世となりインターネットのオンラインで、帰国後すぐその DVD を購入できた。映画の中のアイルランドの自然、時代背景が多少解った今、何度も繰り返し見るはめになった。貧しい市民の反英感情の中、英国軍人と満たされぬ心のアイルランドの娘の不倫がストーリーであった。映画の舞台になった1916 年、アイルランド義勇軍は反英蜂起した。当時の銃弾の跡が柱廊に残っていると知り、ダブリンの中央郵便局を訪れた。イオニア式の美しい建物の一角に、当時処刑された十五人の若者が切手となって販売されていたのである。
それから90年を経て、アイルランドの Enya の音楽のひとつ「Only time」が、中国の女子十二楽坊で演奏され、Celtic Woman のレパートリーの一つ「You Raise Me Up」がフィギュアスケートの荒川静香選手のエキシビジョンの音楽として採用される時代である。この曲や明治17年に訳された小学唱歌「庭の千草」の曲でもわかるようにメランコリーな感傷はアイルランドの曲の典型である。日本人にとっても共有できやすい感情かも知れない。「You Raise Me Up」は19世紀の大飢饉時代にアイルランドからUSAへ移民した人々をモチーフにした歌である。ダブリンの空港のロビーに、元ケネディ大統領の大写真がある。彼の曽祖父はまさにその当時米国に移住しているのである。もっとも彼らは貧困とは関係なかったらしい。
娘の夫の実家及び多くの農家が酪農を主体としている。多雨と、涼しい国にも拘らず冬でも氷点下になるのはまれという気候のせいで、一年中草に溢れている。自然にさかわらない成業である。その町には日本で言うと戦国時代に石で作られた “Rock of Cashel”というどっしりした城が残っている。ヨーロッパの端に位置する意外な古い歴史を持つ小国が、私の日常生活の端々につながっていたのである。
眼を閉じるとどこまでも広がる真緑の牧場、そして真青に澄んだ海が浮かぶ。アイルランドの美しさは、帰国後もしばらく私をとらえて放さなかった。アルバムの一ページ一ぺージに、豊かな自然と温かな人々との出会いが、今も静かに息づいている。
住友化学へ入社三年目の時、東大の功刀教授に黒ものの化学の研究の可能性を問い合わせたことがある。先生の卒業生が住友化学の新居浜にいて、その方を通して真意を尋ねられもした。その方は鹿島から新居浜へ帰った後に上司となる。休職の許可が取れなくて結局うやむやになってしまった。それから一年経った頃副所長から日曜の朝突然電話を受けた。新入社員との懇談会で顔を合わせた縁のみであったのだが、重質油のプロジェクトがあるのだがやってみるかと言われた。それが鹿島に派遣される前の半年前だった。回りまわって重質油からオレフィンガスを作るという K-K (功刀、国井)プロセスに関わることになったのである。
プラントは1980年春に竣工し2年間のテスト運転が実施された。700℃という反応温度で重油を分解するのだが、炭化反応との戦いでもあった。重油は分解してエチレン、プロピレンなどのガスになるとともに安定な炭素へと変化する。この場合炭素というのは炭素原子がお互いに結合した分子量の大きな分子である。言い換えると分解反応と重合反応(コーキング)が平衡して起きるわけである。
炭素の化学は有機化学と無機化学の両方にまたがる現在も非常にホットな化学である。炭素の結合形態により多くの分子がある。分子のサイズは化学屋の間では 10-8 cm Å (オングストローム) の単位で表される。その一桁大きいサイズが10-7 cm または10-9 m であってナノ領域である。炭素はこの領域でチューブ状の形態がありカーボンナノチューブと言われる。サッカーボールのような網目になったものはフラーレンである。層状になったものが良く知られているグラファイト(黒鉛)であり、一層のシート状のものはグラフェンである。一部ダイアモンド状の構造を持つものはダイアモンド状炭素である。
炭素は二酸化炭素に加えて、温暖化の問題とは非常に縁がある。充電、放電を繰り返すことのできる二次電池は電気自動車の要であるが、ナノカーボンはリチウム二次電池の電極に使われる。フラーレンと色素を結合させたものは色素で感度を上げた太陽電池に利用される。ダイアモンド状炭素は潤滑油へ混入させても良い。潤滑性能の良いエンジン油は燃費を上昇させる。言い換えればCO2 排出量を減らすわけでもある。
重質油の熱分解反応は、副生するコーキング反応との戦いでもある。一般に分子が分解する時には、熱を奪う(吸熱反応)。一方、分子がくっつく時には熱を出す(発熱反応)。そのためこのプロセスの重質油の分解においては熱源として加熱したコークスを反応器へ循環させている。コーキング反応で出来た一部の炭素はコークス表面に積層する。一部は分解ガスと共に反応器から排出し冷却してパイプの表面に付着して固まる。一部は分解油と共に反応器から排出して油とのスラリーとなり系内を循環することになる。後でこのプロセスの結果をまとめたいと思うが、このプロジェクトが始まった時、炭素のバランスという極めて基本的な問題は解決されていなかったものと思われる。
鹿島滞在中に初めての海外旅行を計画した。1981年の年末年始である。ただの見学旅行だけではおもしろくないということで、ひとつだけ余分のスケジュールを加えた。
アパラチア山脈はロッキー山脈に比べると規模は小さいのだが、山の少ない東部では国立公園、リゾート地が散在する。ウェストバージニア州は全州をアパラチア山脈に位置する起伏に富む貧しい州のひとつである。そこの州都
Charleston に今は、ダウケミカルに吸収された、ユニオンカーバイドの工場、研究所がそこにあった。そこで、彼らは原油分解の ACR という反応器を開発していたのでそこを1982年1月2日に訪れた。私は、少し結果の出つつあったK-K プロセスの試験結果を紹介した。現在住んでいるオハイオ州の隣の州で、30年後にその 州とCharlestonを再訪できる機会が来た。以下はその時の話である。

(Charleston にあるウェストバージニアの Capital)
Charleston は川沿いの谷間にできた州都としては小さな町である。USAの化学プラントは惜しげもない広大な敷地にあるのが普通だが、ユニオンカーバイド、現在のダウケミカルのプラントは、狭い谷間にある。ハイウェーからも敷地内部を良く見ることができる。狭い土地で、公害問題はどうだったのだろうと思わせる。そこを、奥深く行くと人里離れた小さな町のみとなる。そういうところに Greenbrier Hotel というホテルが忽然と現われるところがある。一泊 $400 の1778 年に建てられた由緒あるホテルで、私みたいな庶民が気軽に泊まるというわけにはいかない。第二次大戦が始まった直後の 1941 年 12 月から 1942 年 6 月まで日本、ドイツ、イタリアの外交官および家族がここに収容されていた。日本人は総勢 400 人いたそうだ。この辺りの経過は柳田邦男の「マリコ」という小説にも出てくる。 ホテルはゴルフ場を含め広大な敷地内にある。

(正面の階段のところで、かって400人全員が記念写真を撮った)
2008年、スモーキーマウンテンへバケーションに行く途中寄ってみた。当時のものが何か残っているかもしれないと期待しながら見学してホテルを出ようとした。がっかりしたような表情を見てか、出口のドアのところにいた美人の案内嬢が声を掛けてくれた。「戦時中、大勢の日本人の外交官が収容されていたはずだが何か残っていないのか」と尋ねると、歴史家にページングで連絡してくれた。ゴルフの見学をしていたにも関わらず博士号を持つ人が駆けつけてくれた。
「マリコ」の両親の話をするとすぐ理解してくれて、私自身その時は名前を思い出せなかったのだが、彼がすぐさま「テラサキ」と返答してくれた。別棟の小さい家が博物館になっていて当時の写真を十点程度見ることもできた。収容されていた人の安全確保の観点から当地のような辺鄙なところが選ばれたということだ。敷地内にかなりの FBI および軍が駐留していたと言うことだが、収容されていた人は比較的自由だったらしい。博物館の隣が子弟のための学校に使われていたという建物である。ホテルの横が 400 人の記念写真を撮った場所である。その写真も残っていて「マリコ」と両親を指摘してくれた。一部の写真は柳田邦男の本にも収められている。
テネシーのスモーキーマウンテンの西にあるさほど大きくない Johnson City という町が、「マリコ」の母親の故郷で、戦後二人でこの町へ日本から戻ってきた。マリコはここにある大学で学んでいる。例の歴史家は母親に会おうと何度か掛け合ったそうだが、思い出したくないということで結局会えなかったそうである。スモーキーマウンテンの反対側はかって、ヨーロッパからの白人に追い出されるまで大勢のチェロキーのインディアンが居住していたところである。彼ら自身が経営する博物館があり、往時を少し見ることができる。
オイルショック後、政府の肝入りで始まったこのプロジェクトは、2年余りのテスト運転を終えて1982年の四月に終了した。以来30年を経ようとしている。以後の情勢変化を織り交ぜてこのプロジェクトの意義などを振り返ってみたいと思う。
このプロセスは炭との闘いであった。炭化水素の熱分解の場合、分解反応と炭化反応が並行して起きる。炭化反応とは芳香族化合物の縮合反応と見なされ、分子量が大きくなる反応であって、分解反応とは全く逆の反応である。
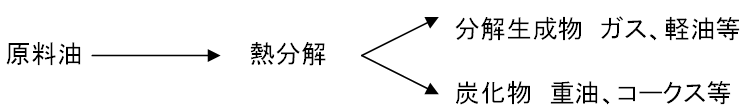
原料の油が重質のものほど炭化反応が顕著になる。炭化反応の生成物はコークスから液状の油まで連続的である。熱媒体のコークス表面に積層していくものからガスと一緒に反応器から飛び出すものまでさまざまである。反応器から飛び出した炭化物は非常に厄介である。配管に付着して最後は非常に硬い炭状のものなるもの、油と一緒にスラリーとなり系内を回るものとがある。スラリーの一部は反応器へリサイクルされるのだが、油分は一度高温で処理されて芳香族性のために炭化反応がさらに促進されることになる。
生成した軽油分は、業界ではリサイクル油とも言われる。蒸留して回収できる油分からは、触媒とともに接触分解するとガソリンができる。この場合の温度は400℃ぐらいなので、リサイクル油を反応器へ戻しても炭化反応は著しくはない。しかし、このプロジェクトのように700℃といった反応温度が高い場合は、炭化反応は非常に顕著である。
テストの結果、配管へ付着したコーキングは深刻なものであった。配管を閉塞寸前まで行った。またリサイクル油はバランスがとれずマイナスの収率となった。系外へ出してタンクへ溜まった油には炭素分がスラリーとして混入していた。タンクの底に沈殿したスラリー分はばかにならない量だったのはずだがこの目でみるチャンスはなかった。
成功、万々歳とプロジェクトが終わったのだが、実は次のような基本的な問題があった。テスト運転では、プロセス内の基本的な炭化反応の収支が理解できなかった。また生成油の物質収支がとれなかった。コーキングの物理的障害を克服できなかった。このプロセスを、装置産業の石油化学へ応用するのは非常に危険である。また、なぜ減圧残油から化学原料を作るとのかいう必然性がない。この問題については次に資源の観点から若干考えてみたい。